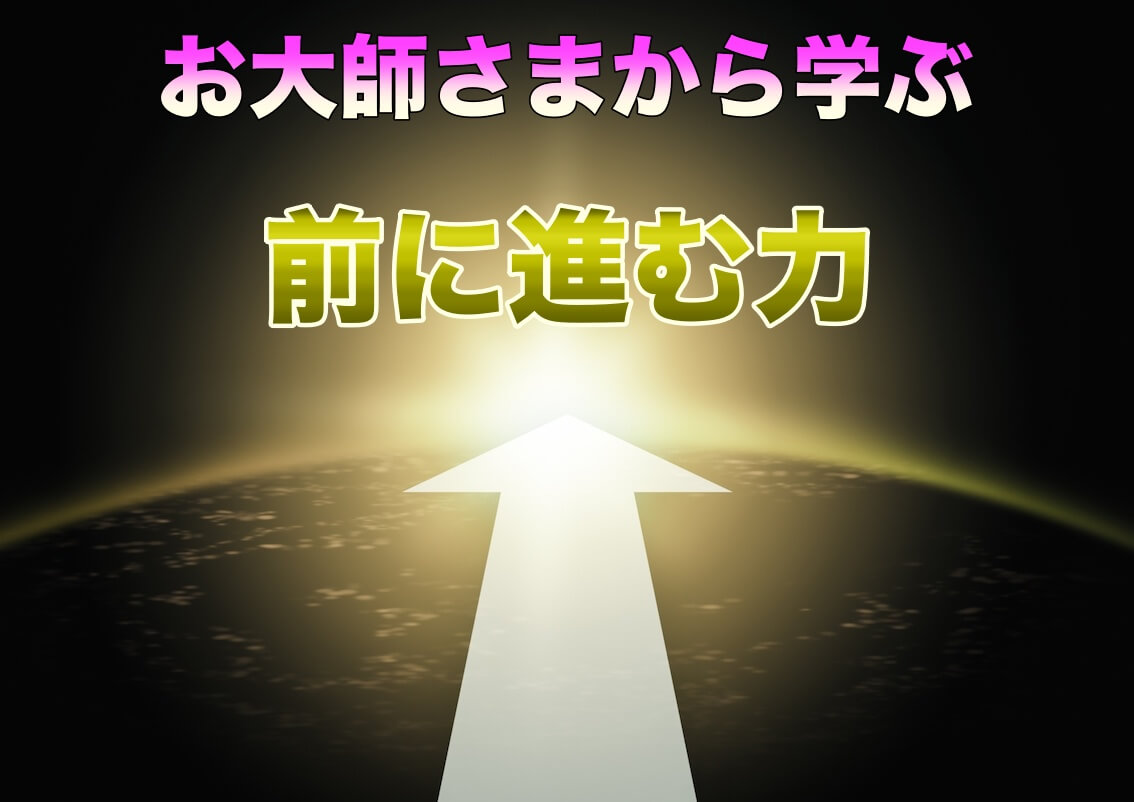こんにちは。広島の作業療法士の川本健太郎です。

今日は、高野山真言宗 僧侶の川本祐道(ゆうどう)として、仏教に関するちょっとした小話(こばなし)をします。
サクッと読めるように心がけていますので、お気軽に読んでみてください。
(*´▽`)ノノ
今日のアイキャッチの画像は、記事内で紹介する東大寺鐘楼(とうだいじしょうろう)の写真です。
(*^-^*)
お寺の『鐘』の意味はなんだろう?
前回のブログでは、「祇園精舎の鐘の声」は実は
木魚の音
だったということをお伝えしました。
↓ ↓ ↓
ところで、そもそもお寺の『鐘』にはどんな意味があるのでしょうか。
お寺では音の出るさまざまな楽器を使います。
これらの楽器のことを総称して
梵音具(ぼんのんぐ)
または
鳴物(ならしもの)
と言います。
梵音具には大きく分けて2つの種類があり
①時刻を知らせたり行事の始まり・終わりを伝えるもの
②仏さまを喜ばせるための各種の法要で演奏されるもの
であり、お寺の『鐘』は①に含まれます。
ちなみに、真言密教では②の法要で使用する道具が非常に多く、遠くまで響く音がするものを用いることが多いので、初めて真言密教系の法要に参加される方からは
「まるでお祭りみたい」
「こんな派手な法要は初めて」
(;゚д゚)ノビックリ!
とよく言われます。
さてお寺の『鐘』が時刻を伝えたり行事の始まり・終わりを伝えるものと分かったところで、少しこの『鐘』に関することについて説明をします。
『鐘』はそれ単独では使うことができないので、なんらかの建物に吊るして使うことが一般的です。
この建物ことを
鐘楼(しょうろう)
と言い、鐘楼に吊るされる鐘のことを
梵鐘(ぼんしょう)
と言います。
有名な鐘楼としては奈良県にある国宝の

東大寺鐘楼
(とうだいじしょうろう)
が有名で、梵鐘の重さは
26トン
もします。
Σ(゚Д゚)スゲェ!!
本来、『楼(ろう)』と名前がつくものは2階建以上の建物のことを言いますが、現代ではこの東大寺の鐘楼のように4本の柱に屋根をかけたものを鐘楼と呼ぶことが多いです。
実際に2階建の鐘楼では東大寺鐘楼と同じく奈良県にある国宝の

法隆寺東院鐘楼
(ほうりゅうじとういんしょうろう)
が有名で、1階部分がスカートのような形をしていることから
袴腰(はかまごし)付き鐘楼
とも呼ばれています(写真出典:ニッポン旅マガジン)。
東大寺鐘楼を例に、鐘楼の各部位の名前を少し紹介しますね。


こうした東大寺鐘楼に代表される建築構造には
非常に重たい梵鐘をしっかりと支える機能
地震が起きた際に揺れの力を分散させる機能
建物そのものの美しさを際立たせるもの
といった特徴があり、ただ単に鐘の音を鳴らすためだけではない
日本建築独特の実用性と美しさを兼ね備えている
と言えます。
皆さんもお寺にお参りされた時、鐘楼あるいは鐘を見かけられたら、鐘の音や建物の構造に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
<お大師さまゆかりの地>
.jpg?resize=515%2C343&ssl=1)
四国霊場八十八ヶ所
第十六番札所
光耀山 千手院 観音寺
(こうようざん せんじゅいん かんのんじ)
観音寺は聖武天皇(西暦701年〜756年)が天平13年(741年)に全国に建立した国分寺・国分尼寺とともに、行基菩薩(西暦668年〜749年)によって建立された由緒あるお寺です。
弘仁7年(西暦816年)にお大師さまが四国霊場の開創のために巡教した際に千手観音像を自ら彫刻して御本尊とされ、また、千手観音の脇侍には悪魔を調伏する不動明王像と国を護ることを祈願して毘沙門天像をも彫刻して納められました。
<約4分半の動画で観音寺の紹介をされています>
戦国時代の兵火によってほぼ全ての建物が消失しましたが、万治2年(1659年)に宥応法師(ゆうおうほうし)によって伽藍が再建され、現在に至っていると伝わっています。
所在地:〒779-3123 徳島県徳島市国府町観音寺49-2
お問い合わせ:088-642-2375(TEL)
交通アクセス:四国八十八ヶ所霊場會
皆さんの貴重なご意見・ご感想、大変参考になりますので、お気軽にコメントなどいただけると嬉しいです。
↓ ↓ ↓
また、ブログランキングにも参加していますので、このブログがお役に立てたと思っていただけるようでしたら、
をポチッと押して応援をしていただけると大変ありがたいです。
最後までブログを読んでくださり、ありがとうございます!








 ブロトピ:ブログ更新しました
ブロトピ:ブログ更新しました ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました! ブロトピ:更新しました
ブロトピ:更新しました ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!